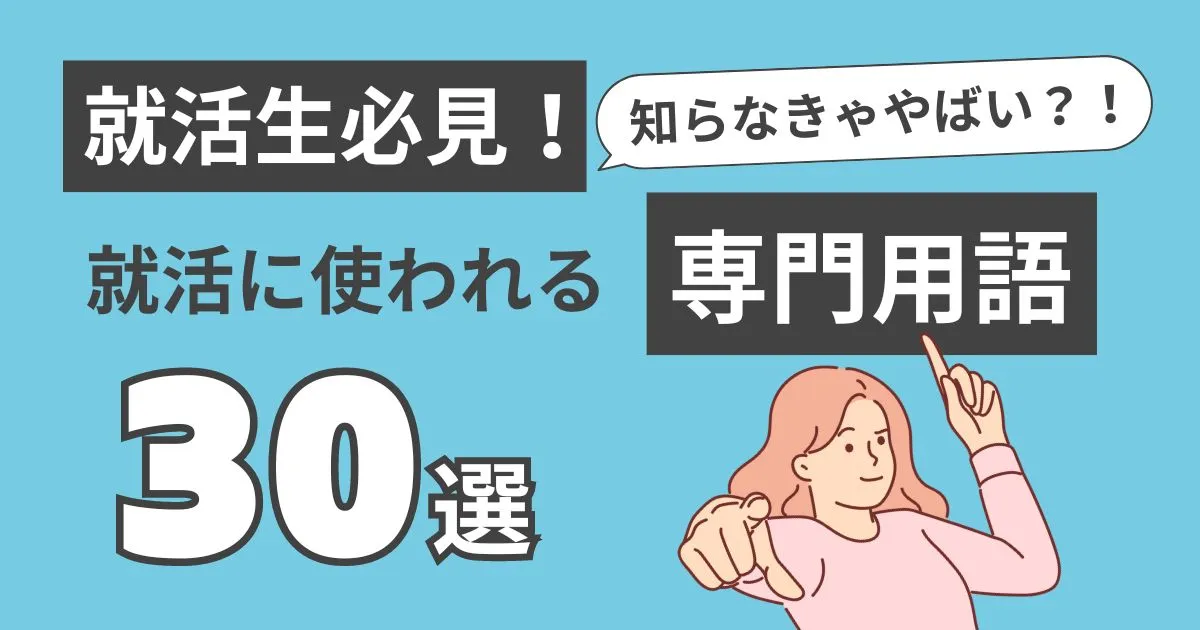【3ステップ】業界研究の効率的なやり方とは?失敗しないためのコツも解説

「業界研究ってどうやればいいの…?」
就職活動を始めたばかりのあなたは、そう思っていませんか?
やみくもに企業を探し始めても、どこから手をつけていいかわからず、時間だけが過ぎていく。気づけば、興味のない企業の説明会に参加し続け、いつの間にか就活迷子になっているかもしれません。
そんな状況を避けるために最も重要になるのが、「業界研究」です。
業界研究は、将来の選択肢を広げ、自分に合った企業を見つけるための羅針盤です。しかし、ただ闇雲に情報を集めるだけでは意味がありません。効率的に、そして自分自身の納得感を高めながら進めるには、正しいやり方を知ることが不可欠です。
この記事では、業界研究を【3つのステップ】に分けて、具体的な進め方と、失敗しないための3つのコツを徹底解説します。この記事を読み終える頃には、自信を持って業界研究を進められるようになっているはずです。
目次
業界研究とは?
業界研究とは、世の中にある様々な業界の動向や特徴、ビジネスモデル、将来性などを深く掘り下げて分析することです。
「IT業界」「金融業界」「メーカー」「商社」といった言葉は聞いたことがあるかもしれません。しかし、それぞれが具体的にどのような仕事をしているのか、今後どうなっていくのかを正確に理解している人は少ないのではないでしょうか。
業界研究は以下のことを意識しましょう。
- 業界の構造を理解すること
- 業界の「常識」を把握すること
- 自分の価値観と結びつけること
1. 業界の構造を理解すること
業界研究は、単に特定の企業を調べることではありません。その業界全体がどのように成り立っているかを理解することが重要です。
たとえば、食品業界であれば、原材料を生産する企業、加工する企業、そして消費者に届ける小売企業など、複数の企業や役割が複雑に絡み合って一つの産業を形成しています。
業界研究を通じて、自分が興味を持つ企業が、その大きな構造の中でどのような役割を果たしているのかを知ることができます。
2. 業界の「常識」を把握すること
各業界には、その業界特有のビジネスモデルや慣習、専門用語、そして課題があります。
これらの「常識」を事前に把握しておくことは、就職活動を有利に進める上で非常に重要です。
たとえば、IT業界であれば「SaaS」や「DX」、金融業界であれば「フィンテック」といった言葉が頻繁に使われます。
業界研究を通じて、これらの専門用語やトレンドを理解しておくことで、面接官との会話がスムーズになり、本気度をアピールできます。
3. 自分の価値観と結びつけること
業界研究は、ただ情報をインプットするだけでなく、自分自身と向き合うための大切なプロセスです。
「この業界のどんな点に惹かれるのか?」「自分が働く上で大切にしたい価値観(安定性、成長性、社会貢献など)は、この業界で実現できるだろうか?」といった問いと向き合うことで、より深く、納得感のある自己分析にもつながります。
4. 業界内の「立ち位置」を分析する
特定の企業を調べる際、その企業が業界内でどのようなポジションにいるのかを理解することが大切です。
業界のリーダー(ガリバー企業)
市場を牽引する存在。ビジネスモデルや戦略が業界のスタンダードになっていることが多いです。
チャレンジャー(追随企業)
リーダー企業に追いつこうと独自の戦略を打ち出している企業。新しい技術やサービスに積極的に投資している場合が多いです。
ニッチプレイヤー
特定の分野や市場で独自の強みを発揮している企業。特定の顧客層に深く刺さるサービスを展開していることが多いです。
これらの立ち位置を理解することで、その企業が今後どのような戦略を取る可能性があるのか、そしてそこで自分がどのような役割を担えるのかをより具体的に想像できます。
5. 業界の「課題」と「チャンス」を見つける
どの業界にも、解決すべき課題や、今後成長する可能性を秘めた分野が存在します。
例えば、
- 課題:少子高齢化による市場縮小、環境規制への対応、デジタル化の遅れなど。
- チャンス:新たなテクノロジーの活用(AI、IoT)、海外市場への進出、新しい顧客ニーズの創出など。
これらの課題とチャンスを把握することで、面接で「この業界の課題を解決したい」といった、より説得力のある志望動機を語るためのヒントが得られます。企業がどのような課題を認識し、それに対してどのような戦略を立てているかを知ることは、皆さんの本気度をアピールする上で不可欠です。
6. 働き方や社風を具体的にイメージする
業界研究は、企業のビジネスモデルだけでなく、そこで働く人々のリアルな姿を想像することも含まれます。
- 働き方:残業時間、リモートワークの有無、仕事の進め方(個人プレーかチームプレーか)など。
- 社風:挑戦を歓迎する風土か、安定性を重視する風土か、上下関係の厳しさなど。
これらの情報を得るには、OB・OG訪問やインターンシップが有効です。実際に働く人に話を聞くことで、入社後の働き方や雰囲気が自分に合っているかを確かめることができます。企業の公式サイトや採用ページでは見えにくい「リアル」な部分を深掘りすることで、入社後のミスマッチを避けることができます。
業界研究は、就職活動の入り口であり、そして自分のキャリアを考える上で欠かせない土台作りと言えるでしょう。
なぜ、業界研究は就活で重要なのか?
「なぜ、わざわざ業界研究なんてするの?」そう思う方もいるかもしれません。しかし、業界研究は皆さんが思っている以上に、就職活動において重要な意味を持っています。
1. 入社後のミスマッチを防ぐため
就職活動の最大の失敗は、入社後に「こんなはずじゃなかった…」と後悔することです。なんとなくのイメージだけで選んだ業界や企業は、実際に働き始めてから大きなギャップに直面する可能性が高いです。
たとえば、「IT業界はかっこいい」というイメージだけで選考を受けても、実際には地道な開発作業や顧客との調整業務がメインかもしれません。業界研究を通じて、その業界のビジネスモデルや具体的な働き方、職場の雰囲気を深く理解することで、入社後のギャップを最小限に抑え、自分に合った企業と出会う可能性が高まります。
2. 説得力のある志望動機を作るため
面接で必ず聞かれるのが「なぜ、この業界を志望するのですか?」という質問です。このとき、「なんとなく興味があったからです」といった浅い回答では、面接官に熱意が伝わりません。
業界の動向や課題、将来性を把握することは、面接での「鋭い質問」や「説得力のある志望動機」につながります。 たとえば、特定の業界が抱える課題を挙げ、その課題を自社のサービスや技術でどのように解決したいかを語ることができれば、皆さんの本気度や熱意は面接官に強く伝わるでしょう。
3. 自分のキャリアプランを明確にするため
業界研究は、単に企業を調べるだけでなく、将来の自分を考えるきっかけになります。
「この業界で働くことで、将来どんなスキルが身につくのか?」「どんなキャリアパスがあるのか?」といったことを知ることで、漠然としていた将来の目標が具体化します。自分の興味や価値観に合った業界を見つけることで、就職活動のモチベーションも向上し、納得のいくキャリア選択ができるようになります。
3つのSTEP!業界研究の進め方は?
業界研究と聞くと、「何から始めればいいかわからない…」と途方に暮れてしまうかもしれません。しかし、以下の3つのステップに沿って進めれば、効率よく進められます。
【STEP1】まずは全体像をつかもう:業界を俯瞰的にリサーチする
まずは、世の中にどのような業界があるのか、全体をざっくりと把握するところから始めましょう。この段階では、特定の業界に絞る必要はありません。
情報取得の方法として以下のものが挙げられます。
- 経済新聞や業界地図を見る
- 就職情報サイトの業界特集を見る
経済新聞や業界地図を見る
新聞の経済面や、書店で手に入る「業界地図」は、全体像をつかむのに最適です。それぞれの業界がどのような企業で構成されているか、業界内の力関係はどうなっているかなどが一覧でわかります。
就職情報サイトの業界特集を見る
「リクナビ」や「マイナビ」といった就職情報サイトには、各業界の概要を解説した特集記事が多数掲載されています。イラストや図解が多く、初心者でもわかりやすいのが特徴です。
【STEP2】気になる業界を深掘りする:具体的なやり方
全体像がつかめたら、少しでも興味を持った業界について、さらに詳しく調べてみましょう。
- 各企業のIR情報を見る
- OG訪問をする・インターンシップに参加する
各企業のIR情報を見る
IR(Investor Relations)情報とは、企業が株主や投資家向けに公開している情報です。企業の公式サイトに必ず掲載されており、経営戦略や財務状況、事業内容が詳しく書かれています。 特に「決算短信」や「有価証券報告書」には、企業が力を入れている事業や今後の展望が具体的に記載されているため、深く企業を理解する上で非常に重要です。
OG訪問をする
実際にその業界で働いている先輩に話を聞くのが最も効果的です。インターネットでは得られない「生の声」を聞くことで、仕事のやりがい、大変なこと、会社の雰囲気などを肌で感じることができます。 OB・OG訪問では、「入社前と入社後のギャップはありましたか?」「この仕事で一番面白いと感じる瞬間はどんな時ですか?」といった、働くリアルな部分を質問してみましょう。
インターンシップに参加する
短期間でも、実際に企業で働く体験は貴重です。社員の一員として業務を体験することで、その業界や企業が自分に合っているかどうかを確かめることができます。 実際に手を動かして働くことで、やりがいや職場の雰囲気を体感できるため、入社後のミスマッチを大幅に減らせます。
【STEP3】業界を比較検討する:自分に合った業界を見つける
いくつかの業界を深掘りしたら、それぞれの業界を比較検討してみましょう。
- 業界の共通点や相違点を洗い出す
- 比較表を制作する
- 業界の「これから」を考える
業界の共通点や相違点を洗い出す
たとえば、「IT業界」と「Web業界」、「金融業界」と「コンサルティング業界」など、似ているようで異なる業界を比較してみると、それぞれの特徴がより明確になります。
比較表を制作する
「給与」「働き方(残業時間など)」「将来性」「仕事内容」といった軸で比較表を作成すると、それぞれの業界の特徴が明確になります。漠然と考えるのではなく、客観的なデータや自分の価値観を元に可視化することで、より納得感のある選択ができます。
業界の「これから」を考える
「今後伸びていく業界はどこか?」「AIやテクノロジーの進化で、将来的に働き方はどう変わるか?」といった視点で考えてみましょう。5年後、10年後の自分を想像しながら業界を選ぶことが大切です。 成長産業に身を置くことで、自身のキャリアアップもスムーズに進む可能性があります。
業界研究を成功させるための3つのコツ
ただ闇雲に情報を集めるだけでは、効果的な業界研究とは言えません。以下の3つのコツを意識することで、より質の高い業界研究ができます。
コツ1:情報を鵜呑みにしない
インターネットや書籍の情報は、あくまで一般的なものです。情報の中には古いものや、企業の良い面だけを強調したものが含まれている可能性があります。
必ず複数の情報源から情報を集め、多角的に分析する姿勢が大切です。
たとえば、企業の採用サイトだけでなく、ニュース記事や競合他社の情報も合わせてチェックすることで、より客観的な視点を持つことができます。
コツ2:自分の興味・価値観と結びつける
業界研究の目的は、単に知識を増やすことではありません。
「なぜ、自分はこの業界に惹かれるのか?」「この業界で働くことで、自分のどんな価値観が満たされるのか?」を常に自問自答しながら進めましょう。
自分の興味や価値観と結びつけることで、表面的な情報だけでは見えてこない、本当に自分に合った業界を見つけることができます。
コツ3:アウトプットの場を作る
調べて終わり、では意味がありません。友人や家族に調べたことを話したり、就職活動のイベントでアウトプットする場を設けてみましょう。
人に説明することで、自分の理解が深まり、新たな気づきが得られることもあります。また、誰かに話すことで、考えが整理され、志望動機を言語化する練習にもなります。
就活を有利に進めるならガクチカを極めるべき!
業界研究が重要であるのと同様に、就職活動では「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」も非常に重要視されます。どれほど業界や企業を深く理解していても、それを伝えるための材料がなければ、説得力のあるアピールはできません。
なぜガクチカが重要視される?
企業はガクチカを通じて、皆さんの「物事に対する主体性」「課題解決能力」「協調性」といった、社会に出てから必要になるスキルやポテンシャルを測ろうとしています。
単に「サークル活動を頑張りました」という事実を述べるだけでは、面接官の心には響きません。
重要なのは、「なぜその活動に力を入れたのか」「どのような目標を立て、どんな課題に直面したか」「その課題をどう乗り越え、何を学んだか」というプロセスです。
たとえば、「チームの練習効率を上げるために、データ分析を導入した」というガクチカは、単に「チームをまとめた」という話よりも、論理的思考力や実行力を具体的に示すことができます。
企業は、皆さんが過去に発揮した能力を、入社後も再現してくれることを期待しているのです。ガクチカは、皆さんの個性や強みを最も雄弁に語るための、大切なエピソードなのです。
希少価値のあるガクチカを手に入れるならGeekSalon!
「ガクチカに自信がない…」「他の就活生と差をつけたい」と悩んでいる方もいるかもしれません。そんな方は、プログラミング学習という選択肢を考えてみませんか?プログラミングスキルは、IT業界はもちろん、今やあらゆる業界で求められる希少価値の高いスキルです。
GeekSalonは、プログラミング未経験からでも最短1ヶ月でオリジナルのWebサービスやアプリ開発に挑戦できるプログラミングスクールです。

GeekSalonの受講生の多くは、就活生です。他の就活生と差別化できるガクチカを作るために受講している方も多くいらっしゃいます。
メンターが徹底的にサポートするため、専門知識がなくても安心してスキルを身につけられます。
GeekSalonでプログラミングを学ぶことは、単なるスキル習得にとどまりません。 ゼロから一つのサービスを企画し、作り上げる過程で、「課題発見能力」「論理的思考力」「やり抜く力」といった、企業が求めるポータブルスキル(どんな業界でも通用するスキル)を総合的に養うことができます。
GeekSalonでプログラミングを学び、他の就活生とは一味違う、説得力のあるガクチカを手に入れて、就職活動を成功させましょう!