JavaScriptは簡単って本当?初心者がつまずかない学習ステップとコツを解説

「プログラミングを学ぶなら、まずはJavaScriptから始めてみると良い」と言われたことはありませんか?
JavaScriptは、Web制作やアプリ開発に欠かせない言語として、多くの教材や入門書で取り上げられています。学習環境が整っており、すぐにブラウザで試せる手軽さから「初心者向け」と紹介されることも多くあります。
しかし、実際に学び始めてみると「思っていたより難しい…」と感じる人も少なくありません。
本記事では、JavaScriptの基本的な特徴やできることを解説したうえで、初心者がつまずきやすいポイントや、効果的な学習ステップについて詳しくご紹介します。
これからJavaScriptに挑戦して見ようと思っているけれど、ハードルが高いという方はぜひ参考にしてみてください。
目次
JavaScriptってどんなプログラミング言語?
プログラミングに触れたことがない方にとって、
「そもそもJavaScriptって何ができるの?」「どういうときに使うの?」
と疑問に思うこともあるかもしれません。
ここでは、JavaScriptがどのような言語なのかを初心者の方にもわかりやすくご紹介します。
JavaScriptでできることとは?

JavaScriptは非常に多彩な機能を持つプログラミング言語で、Web開発の現場ではさまざまな用途に使われています。ここでは代表的なものを4つ紹介します。
- 動的なWebページの作成
- 非同期通信(Ajax)
- サーバーサイドの処理
- モバイルアプリやデスクトップアプリの開発
動的なWebページの作成
Webページに動きをつけることができます。ユーザーの操作に応じて画面の内容を変えたり、アニメーションを付けたりすることができます。
たとえば、クリックで画像が切り替わったり、ボタンを押すとメニューが開閉したりといったことができるようになります。
また、フォームの入力チェックなども行えます。ユーザーが入力した情報をリアルタイムで検証し、エラーの有無を表示することが可能です。これにより、送信前に入力ミスを防ぐことができます。ユーザー名の制約やパスワードのチェックなどに用いられています。
非同期通信(Ajax)
ページ全体を再読み込みすることなく、サーバーとデータのやり取りができるため、ページのローディングなどユーザーの待ち時間が減るためにユーザー体験を向上させることができます。SNSの「いいね!」やコメント機能などもこの技術を使っています。
サーバーサイドの処理
JavaScriptは元々はブラウザ上で動く言語ですが、「Node.js」という技術を使うことで、サーバーという別の場所でも動かせるようになります。よって、Webアプリの仕組み全体をJavaScriptだけで作ることもできます。
モバイルアプリやデスクトップアプリの開発
React NativeやElectronといったフレームワークを使えば、JavaScriptでスマートフォンアプリやデスクトップアプリを作ることもできます。
JavaScriptを使うことで他にもさまざまなことができるので、以下の記事で紹介している内容もご覧ください。
JavaScriptって簡単に習得ができる?
「JavaScriptは簡単に習得できるの?」と気になる方も多いでしょう。
結論から言うと、まったくの初心者にとって「簡単」と断言するのは難しいところがあります。
確かに、JavaScriptは環境を整えやすく、コードを書いてすぐにブラウザ上で動きを確認できるため、学習のスタートとしては取りかかりやすい言語です。
また、オンラインで無料の教材や動画が豊富に揃っているのも学びやすいポイントのひとつです。
しかし、実際にプログラミングの基礎を理解し、しっかりと使いこなせるレベルに到達するには、一定の時間と努力が必要です。
特に、初心者がつまずきやすい文法や概念が多く、慣れるまでは理解に時間がかかることもあります。
なぜJavaScriptが難しいと感じるのか、以下の記事で詳しく書いているので、その理由について気になる方はチェックしてみてください。
JavaScriptを学ぶ際に初心者がつまずくポイントとは?
JavaScriptは魅力的で実用性の高い言語ですが、初めて学ぶ方にとっては、いくつかつまずきやすいポイントがあります。これらのポイントをあらかじめ知っておくことで、スムーズな学習につながるはずです。ここでは、初心者が特に戸惑いやすい3つの要素について解説します。
変数の扱いやスコープ(let、var、const)
JavaScriptでは変数を宣言する方法として var、let、const の3種類がありますが、それぞれの使い方とスコープ(有効範囲)に違いがあるため、初学者にとって混乱のもとになります。
- letとconstはブロックスコープを持ち、より厳密な管理ができる
- constは定数として使うため、再代入ができない
- varは古くから使われてきたキーワードで、関数スコープを持つ
たとえば、同じ変数名を var で複数回宣言してしまってもエラーにならないなど、意図しない挙動が起きやすく、「なぜこうなるのか」がわかりにくい部分です。特にスコープの概念は、初心者が最初につまずきやすい重要ポイントのひとつです。
非同期処理(Promise、async/await)
JavaScriptでは、サーバーからのデータ取得やファイルの読み込みなど、「結果がすぐに返ってこない処理」を行う場面が多くあります。これらの処理を扱うために使われるのが「非同期処理」という仕組みです。
非同期処理では、処理の完了を待ってから次のステップに進むような書き方が必要になります。この考え方は初心者には直感的にわかりづらく、つまずきやすいポイントのひとつです。
Promiseは、非同期処理の「成功」や「失敗」を受け取るための仕組みで、処理の流れを整理する役割を果たします。さらに、async/awaitを使えば、非同期処理をまるで通常のコードのように書くことができ、コードの見通しが良くなります。
たとえば「ネットショップで商品情報を読み込む」場面を想像してみてください。ページを開いたときに、まずサーバーから商品のデータ(商品名、価格、購入可能かどうかなど)を取りに行き、そのデータが返ってきたら画面に表示する、という流れになります。データの取得が終わるまでawaitで待機し、その後の処理を順番に進めることで、複雑になりがちな非同期の流れをシンプルに書けるようになります。
ただし、Promise の基本的な仕組みや async/await の動作を理解していないと、「なぜこのタイミングで実行されないのか」「エラー処理がうまくいかない」といった壁にぶつかることもあります。
非同期処理はWeb開発では欠かせない要素ですが、理解するまでに少し時間がかかるため、初学者が苦戦しやすいテーマです。
thisの挙動や関数の扱いに混乱しやすい
JavaScriptの学習を進める中で、多くの初心者が混乱しやすいポイントのひとつが「this」というキーワードの扱いです。
JavaScriptにおけるthisは、「今いる場所(実行されている状況)によって、意味が変わる」という特徴を持っています。同じコードでも、関数の書き方や呼び出し方によって、thisが指すものが変化するため、直感的に理解するのが難しいと感じる方も少なくありません。
たとえば、通常の関数ではthisが「呼び出し元のオブジェクト」を指しますが、アロー関数(=>)では外側のスコープにあるthisをそのまま引き継ぐという特徴があります。
また、関数そのものも複数の書き方があり、
- 通常の関数宣言(function)
- 関数式(変数に関数を代入する)
- アロー関数(=> を使った記法)
といった違いを理解しないまま書き進めてしまうと、「なぜかエラーになる」「期待した動きをしない」といった問題に直面します。
このように、thisの意味が文脈によって変わること、そして関数のバリエーションが多いことは、JavaScriptの柔軟さの一面であると同時に、初学者にとって混乱を招きやすい要素でもあります。
JavaScriptを習得するための5ステップ!
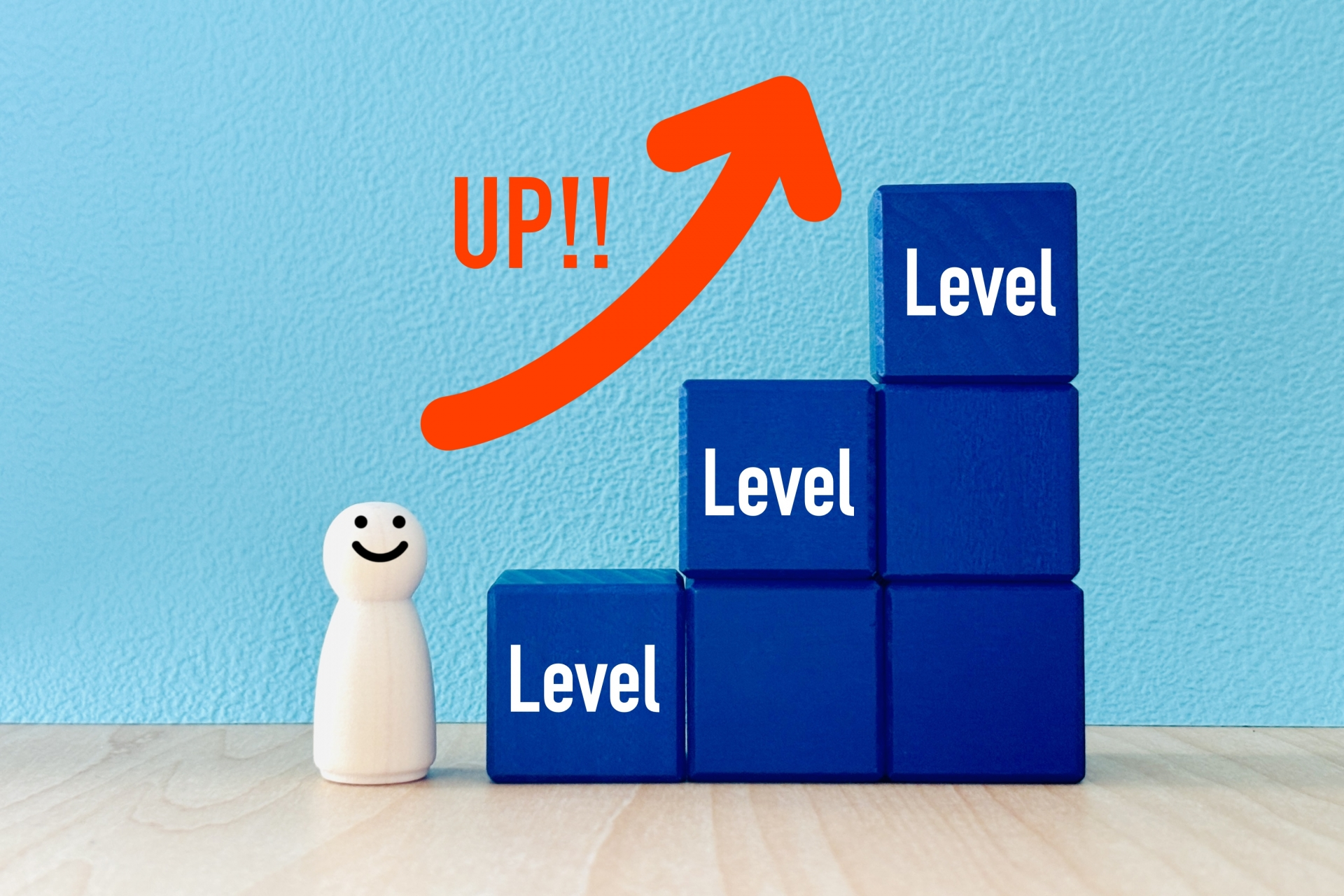
JavaScriptは、独学でも学びやすい反面、幅広い知識と実践力が求められる言語です。やみくもに勉強するよりも、順序立ててステップを踏むことで、つまずきを減らし、効率的にスキルを伸ばすことができます。
ここでは、初心者が無理なくJavaScriptを習得するための基本的な5ステップをご紹介します。
ステップ1:JavaScriptの基礎文法を理解する
まずは、JavaScriptの基本的なルールや記述の仕方を学ぶことから始めましょう。
- 変数(let、const、var)の使い方
- 条件分岐(if、switch)
- 繰り返し処理(for、while)
- 関数の書き方と呼び出し方
この段階では、「コードがどう動くのか」を理解することが重要です。難しい言葉や理論にこだわらず、小さなコードを実際に動かしてみることが効果的です。
ステップ2:DOM操作を学ぶ
JavaScriptの醍醐味のひとつが、Webページ上の要素(テキストや画像、ボタンなど)を動かせることです。
- document.querySelector() を使った要素の取得
- クリック時に表示を切り替えるイベント処理
- テキストやスタイルの変更
これらを通して、「自分が書いたコードでWebページが動くようになる」という体験を積みましょう。初めてJavaScriptの面白さを感じられるステップです。
ステップ3:非同期処理を理解する
ある程度の基礎が身についたら、Web開発には欠かせない「非同期処理」の考え方にチャレンジしてみましょう。
- Promiseとthen()の使い方
- async/awaitによるわかりやすい書き方
- fetchを使ったAPI通信
このステップでは、「時間のかかる処理」とどう向き合うかを理解することがポイントです。ここを乗り越えると、一気に実践的な開発が視野に入ってきます。
ステップ4:ミニアプリを作ってみる
学んだ知識を活かして、簡単なアプリを自分の手で作ってみるのが最も効果的な学習法です。
例としては、「タスク管理アプリ」「おみくじアプリ」「天気情報を表示するアプリ(API利用)」など、小さくても実用的なものを自作することで、知識の定着がぐっと深まります。
ステップ5:コードの整理・保守を意識する
ある程度コードが書けるようになったら、可読性や再利用性を意識した書き方に進んでいきましょう。
- 関数の分割と再利用
- モジュール化の考え方
- デバッグやエラー処理の習慣
プロとしてコードを書く際に重要となる「読みやすさ」「管理のしやすさ」は、最初のうちから意識しておくと大きな成長につながります。
これらのステップをひとつひとつ丁寧にこなしていけば、初心者の方でも着実にJavaScriptを使いこなせるようになります。焦らず、着実に学びを積み重ねていきましょう。
JavaScriptを効果的に学習する方法とは?
JavaScriptを習得するには、地道な学習の積み重ねが欠かせません。ですが、効率よく学ぶためには、自分に合った教材や学習スタイルを選ぶこともとても大切です。
ここでは、初心者の方でも取り組みやすい4つの主な学習方法について、それぞれのメリット・注意点を踏まえてご紹介します。
- Webサイト(無料・オンライン教材)
- 動画(YouTube・オンライン講座)
- 書籍(入門書・実践書)
- プログラミングスクール(本気で習得したい人向け)
Webサイト(無料・オンライン教材)
インターネット上には、JavaScriptの基礎を学べる無料の学習サイトが豊富に存在します。
以上に挙げたようなサイトが代表的です。
Web教材を活用するメリットとしては、無料または低価格で学べる点が挙げられます。中にはブラウザ上でそのままコードを実行できる教材も多く、思い立ったときにすぐ試せる手軽さも魅力です。
また、進捗状況の管理や、初級・中級・上級といったレベル別のカリキュラムが整っているサービスも多く、学習の段階に応じて適切な内容に取り組むことができます。
一方で、注意点もあります。自分のペースで進められる反面、わからない部分でつまずいてしまうと、誰にも相談できず学習が止まってしまうことがあります。また、インプット中心の内容になりやすいため、実践的なスキルを身につけるには、別途、アウトプットの機会(自分で何かを作ってみるなど)を意識的に設けることが大切です。
動画(YouTube・オンライン講座)
最近では、YouTubeやUdemyなどの動画教材も人気です。視覚的に学べるため、初心者にも非常にわかりやすい方法です。
動画教材の大きなメリットは、実際の画面や動きを見ながら学習できる点です。
コードの入力から実行結果までの流れを視覚的に確認できるため、初心者でも理解しやすく、学習のハードルを下げることができます。
また、つまずきやすいポイントについても、実演を交えながら丁寧に解説されている動画が多く、独学では気づきにくい細かな点までカバーできるのが特徴です。さらに、自分のペースに合わせて動画を再生・一時停止できるため、わからない箇所を繰り返し確認しながら進められるのも利点です。
ただし注意点として、動画を見ているだけで「わかったつもり」になってしまうことも少なくありません。実際に手を動かしてコードを書いてみることを併せて行わないと、理解が定着しづらくなります。また、動画の質にも差があり、情報が古かったり、説明がわかりにくかったりするものもあるため、信頼できる教材を選ぶことが大切です。
書籍(入門書・実践書)
体系的に学びたい方には、書籍による学習も有効です。紙の本や電子書籍には、初級から中級者向けまで幅広いラインナップがあります。
書籍を使った学習のメリットは、情報が体系的に整理されているため、基礎から順を追って理解を深められる点です。多くの入門書は初心者を想定して構成されており、概念の説明から実践的なコード例まで丁寧に解説されています。そのため、初めてプログラミングに触れる方でも安心して学び始めることができます。
また、信頼性の高い内容が多く、読み返しや復習にも適している点も魅力です。紙の書籍であれば、インターネット環境がない場所でも学習を進められるため、通学や移動中などのスキマ時間にも活用できます。
ただし注意点として、他の手段同様で本を読むだけで満足してしまい、実際にコードを書いてみる機会が少ないと、なかなか理解が定着しません。知識として覚えていても、自分で手を動かして試さないと、いざというときに使いこなせないこともあります。また、古い本の場合はJavaScriptの仕様や記述方法が現在と異なることもあるため、購入時には発行日や内容の更新状況を確認することが大切です。
プログラミングスクール(本気で習得したい人向け)
「独学で挫折した」「自分ひとりでは限界を感じる」という方におすすめなのが、プログラミングスクールです。講師のサポートを受けながら、実践的な課題やチーム開発を経験できる点が魅力です。
プログラミングスクールで学ぶ最大のメリットは、「わからないことをすぐに質問できる環境」が整っている点です。独学でつまずきがちなポイントも、講師やメンターのサポートによってその場で解決できるため、学習がスムーズに進みます。また、定期的な面談や進捗管理の仕組みがあるスクールも多く、モチベーションを保ちながら継続しやすいのも魅力です。
さらに、多くのスクールでは現場で求められる実践的な内容を重視しており、就職や副業にもつながるスキルを効率的に習得できます。ポートフォリオ制作やキャリア支援までサポートしてくれるところもあり、学んだ内容をそのまま次のステップに活かしやすい点も大きな強みです。
一方で、他の学習手段と比べて費用はやや高めに設定されていることが多いため、コスト面はしっかりと検討しておく必要があります。また、スクールによってカリキュラムの内容やサポート体制には差があるため、「自分に合った環境かどうか」を事前に比較・確認してから選ぶことが大切です。体験や無料カウンセリングを活用して、納得したうえで始めるとよいでしょう。
それぞれの学習方法には、得意・不得意があります。「とにかく始めたい」「基礎をしっかり固めたい」「実務に使える力を身につけたい」など、自分の目的に合った学び方を選ぶことが、挫折しないポイントです。
最終的には、どの手段においても実際に手を動かすということが重要になってきます。どの手段を選んだとしてもしっかりと手を動かしてみましょう。
本格的にJavaSciptを学びたい方は、プログラミングスクールがオススメ!
プログラミングスクールがオススメな理由は?
独学でJavaScriptを学ぶのももちろん可能ですが、効率よくスキルを身につけたいなら、プログラミングスクールの活用が非常に効果的です。ここでは、スクールがなぜおすすめなのか、主な理由をいくつかご紹介します。
- 学習のモチベーションを維持しやすい
- わからないことをすぐに質問できる
- 実践的な課題やチーム開発が経験できる
学習のモチベーションを維持しやすい
スクールでは、学習計画が明確に決まっているため、途中で挫折しにくく継続しやすい環境が整っています。自分ひとりで勉強するとどうしても怠けがちですが、周囲に同じ目標を持つ仲間やメンターがいることで、自然とモチベーションを保てます。
わからないことをすぐに質問できる
独学だと疑問点がなかなか解決できずに停滞してしまいがちですが、スクールでは講師やメンターに直接質問できるため、疑問をすぐに解消できます。理解が浅いまま進むことがなく、効率的に知識を深められます。
実践的な課題やチーム開発が経験できる
多くのスクールでは、実際の開発現場に近いカリキュラムが組まれており、実践的な課題やグループでのチーム開発を体験できます。これにより、技術だけでなくコミュニケーション力や問題解決能力も鍛えられ、転職や就職に役立つ実践力が身につきます。
大学生がWeb開発を学ぶなら、GeekSalonがオススメ!

GeekSalonのWebExpertコースでは、JavaScriptだけではなく、近年人気上昇中のReactというライブラリに沿って開発を進めるため、最新の流行のライブラリも同時に学べます。
GeekSalonでは、プログラミング未経験の方でも3ヶ月の短期集中型で自分だけのオリジナルアプリを作成することができ、一人一人に担当メンターがつくため、わからないこともすぐに聞くことができます。
「初心者向け」と紹介されることも多いJavaScriptですが、実際に学んでみると、変数の扱いやスコープ、非同期処理、thisの挙動など、独特なルールや考え方に戸惑う場面が少なくありません。
人それぞれ合う合わないがあるので、自分に合った進め方を探しながら、実際にコードを書いていくことが習得するための近道です。
「JavaScriptは難しいかもしれないけれど、しっかり学べば必ず身につく」──この記事が、そんな一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。






